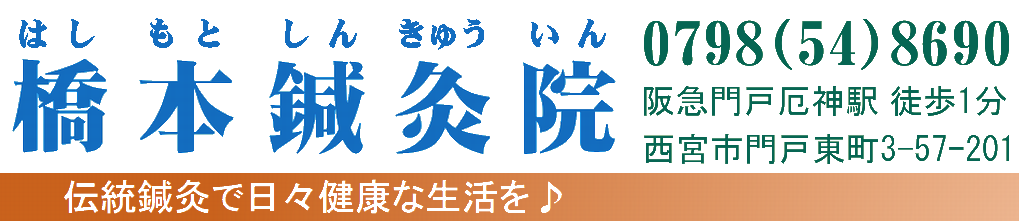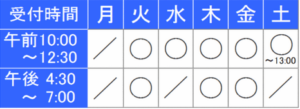片頭痛とは
片頭痛【一般社団法人 日本神経学会】
片頭痛(偏頭痛)という名称は頭の片側が痛むことに由来しますが、実際には4割ちかくの片頭痛患者さんが両側性の頭痛を経験しておられます。片頭痛は前兆の有無と種類により「前兆のある片頭痛」と「前兆のない片頭痛」などに細分類されています。疑い例を含めると、年間有病率は8.4%と推定され、かなり患者数が多い疾患です。また、片頭痛は女性に多いのも特徴です。
前兆は、頭痛より前に起こる症状で、キラキラした光、ギザギザの光(閃輝暗点)などの視覚性前兆が最も多くみられます。通常は60分以内に前兆が終わり、引き続いて頭痛が始まります。漠然とした頭痛の予感や、眠気、気分の変調などは前兆と区別して予兆といいます。
片頭痛発作は通常4~72時間続き、片側の拍動性頭痛が特徴です。頭痛の程度は中等度~高度で日常生活に支障をきたします。また、階段の昇降など日常的な運動により頭痛が増強することも特徴のひとつです。悪心(吐き気)、嘔吐を伴うことが多く、頭痛発作中は感覚過敏となって、ふだんは気にならないような光、音、においを不快に感じる方が多いです。
西宮の橋本鍼灸院の症例
片頭痛は以下の症例のように、下半身の弱りがあって上下のバランスが悪くて上半身が緊張しやすい体質の方や、体力が低下して気血のバランスを崩している方に多く見られます。症状の原因は下半身の弱りや体力低下なので、足のツボを用いて鍼をし、上下のバランスをとり、また気血を補う施術をしていきます。同時に散歩を毎日継続すると再発しにくくなります。ストレスを避けるのも大事ですね。鍼灸は副作用もなく安心して受けることができます。
■30代女性:2年前より、疲れたとき、天気の悪い時、生理前後に片頭痛が起こるようになる。服薬すると少しましだが、なかなか良くならないので、来院される。身体をみると、舌は先端が赤く、脈は弦脉といって力強い脈を打っていました。足は冷えて手は熱く、全身のツボの状態も緊張傾向でした。以上から体力があって、ストレスなどから上半身が過緊張となり起こった片頭痛としました。
ツボは、背部の最も緊張したところを用いました。鍼の後、脈・ツボの緊張は緩み、来院時にあった痛みは少し軽減しました。15回ほど施術を継続されました。
■40代女性:10年以上前から疲れたり天気が悪いと片頭痛とのぼせが起こるようになる。服薬は胃が痛むのであまりしていない。また慢性の腰痛がある。症状の改善を希望されて来院される。
ツボの状態は、上半身が緊張していて、下半身は弛緩傾向でした。脈は下半身を示す場所が弱く、腎虚と思われました。鍼は足の「腎」の働きを補うツボにしました。
■50代女性:20代の頃より天気の下り坂に片頭痛、目がチカチカする症状がでる。
身体を見ると上半身がひどく緊張して、下半身は弛緩して弱っていました。上下のバランスをとるように、鍼を週に1回来院され10回ほど継続されました。
※記載の西宮・橋本鍼灸院の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。
片頭痛の東洋医学に基づく鍼灸
低気圧の接近➡最初は交感神経が亢進➡その後副交感神経が亢進して、頭部の血管が拡張・三叉神経が過敏な状態になる➡片頭痛の発症。
低気圧の接近➡血管・細胞から水分が漏れだし浮腫みを頭皮にも生じる➡三叉神経への刺激➡片頭痛の発症。
以上の生気象医学でのメカニズムは、東洋医学では、低気圧の接近で身体の陽気が盛んになり、続いて反動で陰気が過度に盛んになった時に、血(血は陰性)が上に昇る為と考えます。また浮腫(水も陰性)も発症に影響します。健康な人では、少しくらいの気圧変動では、症状がでませんが、過敏な方は症状が出やすくなります。この過敏さは、ベースに気血の弱りがあると考えます。
気血の弱りを改善➡太白、三陰交、太渓穴で気血を補う。
上に昇った気血を下げる➡照海、関元、気海穴で気血を下げる。
浮腫みを取る➡陰陵泉、照海などで水分を排出させる。
繰り返し、片頭痛が起こりやすい人は、気血の弱りを徐々に補っていく必要があります。橋本鍼灸院では、各人の体質や感受性をよく調べて適切なツボを厳選して施術していきます。根気よく鍼をして発症しにくい身体つくりをしていきましょう。
片頭痛が季節の変わり目に起こりやすい理由
片頭痛が季節の変わり目に起こりやすいのは、気温や気圧の変化が大きく、自律神経や血管が過敏に反応するためと考えられています。詳しく解説します。
1 気圧変化と片頭痛
気圧が下がると脳血管が微妙に拡張し、三叉神経血管系が刺激される遠方の台風や低気圧でも 「気圧さざ波」によって血管が揺さぶられることがある感受性の高い人は微小な変動でも片頭痛を誘発します。
低気圧が接近すると、身体の外側からかかる圧力が低下します。これにより、体内の水分が細胞や血管の外に漏れ出しやすくなり、むくみが生じます。この現象は、主に自律神経の乱れと体液の分布変化という2つのメカニズムによって引き起こされます。全身のむくみと同様に、頭皮でもむくみは生じます。頭皮がむくむと、頭皮下の血管や神経が圧迫され、血流が悪化します。片頭痛は、脳の血管が拡張することで引き起こされると考えられており、むくみによる圧迫が血管の拡張と収縮のバランスをさらに乱し、痛みを誘発する可能性があります。また血管から漏れ出た水が三叉神経を刺激して痛みを誘発しやすくなります。
2 気温変化と自律神経
急な気温変化は自律神経に負担をかける
交感神経 : 血管収縮・ 熱保持
副交感神経 : 血管拡張・リラックス
切り替えがうまくいかないと、血管が過敏に反応 → 頭痛・倦怠感
3 季節の変わり目の特徴
春・秋は特に気温・湿度・気圧が変動しやすい
体温調整・血圧調整の自律神経負荷が増える
睡眠不足や寝室環境の影響も重なると、片頭痛リスクがさらに上昇
4 まとめ
気圧変化➡血管拡張・浮腫の発生➡三叉神経刺激➡片頭痛誘発
気温変化➡自律神経切り替え負荷 ➡ 血管反応・ほてり・頭重
季節の変わり目に上記が重なりやすく、 症状出現率が高くなります。
💡ポイント:
季節の変わり目に片頭痛が出やすいのは 気圧・気温の変化による自律神経・血管の過敏反応 が主な原因
日常でできる予防は、睡眠・寝室環境・呼吸法・軽い運動・ツボ刺激 で自律神経を安定させること