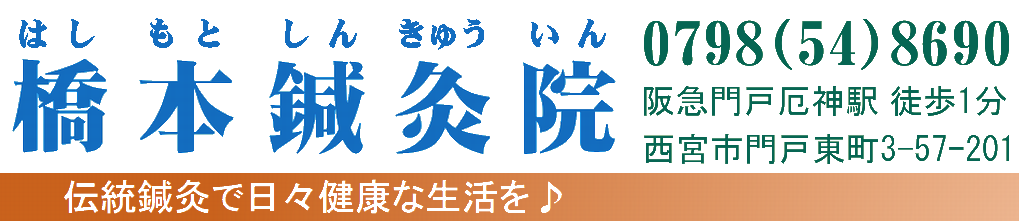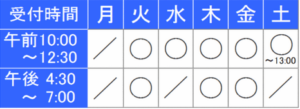過敏性腸症候群は大腸に腫瘍や炎症など症状の原因となるような病気がないのに、おなかの調子が悪く痛みが続いたり、便秘や下痢などの症状が数ヵ月以上にわたって続く消化管の機能障害の疾患です。下に西洋医学の診断、治療を引用しています。原因ははっきりとわかっていません。
🟢東洋医学から考えると西宮の橋本鍼灸院では、身体の緊張をとる鍼(疏肝理気といいます~膈兪・肝兪・百会などを用います)と胃腸の働きをよくする対応(脾胃の働きを改善する太白穴・脾兪穴などを用いる)で症状が落ち着くことから、ストレスと胃腸の機能障害が大きな原因と考えます。下に東洋医学に基づく鍼灸施術について記載しました。
症例
■10代男子 ひどい腹痛が発症し、当初細菌性大腸炎と言われるが、炎症反応がなくなっても登校できないほどの腹痛が継続する。問診と体表観察所見から、ストレス性の腹痛と考える。身体のつよい緊張があるので、それを緩める鍼を行い、ゆっくりと散歩を長く歩くように指導する。30回ほどで施術を終了としました。
■10代男子 色々なストレスから登校すると腹痛が起こるようになる。整腸剤などをもらうがあまり効果がない。週に半分くらい休むのでなんとかしてほしいと来院される。身体をみると脈は固く、全身の筋肉は緊張していて、過緊張の状態だったので、身体全体を緩めるために背部のツボに鍼をする。鍼をすると脈は柔らかくなり、筋緊張も緩和される。来院ごとに徐々に症状は和らぎ、腹痛は時々おこる程度になる。症状が再発しないように時々来院して体調管理をしています。
■40代男性 10年以上前から、緊張する場面で腹痛、我慢できない急な下痢が起こる。仕事中に起こるのでとても困っていました。身体の状態をみると、ストレスで背部と手足のツボが緊張していることと、胃腸のツボが弛緩して弱っていました。背部で緊張を緩め、足のツボで胃腸の働きを改善するようにしたところ、徐々に症状が緩和して、腹痛はほぼなくなり軟便程度の状態になりました。
※記載の西宮・橋本鍼灸院の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。
過敏性腸症候群(IBS)の東洋医学に基づく鍼灸
1. 東洋医学における過敏性腸症候群の捉え方
東洋医学では、IBSは単一の病気として扱うよりも、脾・胃・肝・腎などの臓腑の機能失調と気血の停滞として理解します。
◎主な病因・病機
〇脾虚(ひきょ)
脾は消化・吸収を司る臓腑。脾虚になると、消化不良、下痢、軟便、腹部膨満感が出やすい。
体力低下や慢性疲労も伴うことが多い。
〇肝気鬱結(かんきうっけつ)
肝は気の疏泄(巡らせる作用)を担当。
ストレスや情緒不安定で肝気が鬱結すると、腹部の張り、ガス、便秘や下痢の交互出現が起こる。
〇腎虚・腎陽虚
慢性IBSで冷えや腰背痛、疲労感を伴う場合に関係。
〇痰湿(たんしつ)停滞
水分代謝が乱れると、湿痰が腸内に停滞して腹部膨満や下痢の原因となる。
2. 鍼灸の施術方針
(1) 弁証施灸
東洋医学では、患者の体質と症状のパターンに応じて施術を決定します。
病理パターン 主な症状 鍼灸治療の方向性
〇脾虚型 下痢・軟便・倦怠感 脾を補う・腸の運化を改善
〇肝気鬱結型 腹部張満・便秘と下痢交互 肝気を疏通・気の巡りを良くする
〇腎虚型 冷え・腰背痛・慢性下痢 腎陽を補い、腸運動を安定
〇痰湿停滞型 膨満感・軟便・むくみ 水分代謝を整える・湿痰除去
(2) 主な鍼灸ツボ
◎脾虚型
足三里(ST36):消化吸収機能の改善
公孫(SP4):脾胃の気を整える
三陰交(SP6):血・気の調和、下腹部の症状改善
◎肝気鬱結型
太衝(LR3):肝の気の流れを疏通
中脘(CV12):胃の気を整える
陰陵泉(SP9):湿痰の排除補助
◎腎虚型
腎兪(BL23):腎の気を補う
命門(GV4):腎陽を強化
関元(CV4):腎を温め、気血を補う
◎痰湿停滞型
水分(CV9):水分代謝調整
中脘(CV12):湿痰の除去
豊隆(ST40):湿痰の除去、脾胃機能の補助
3. 施術の手技・方法
◎鍼法
浅刺・中等深刺:腹部や下肢の経穴を中心に
捻転刺激や補瀉操作で、気血の流れを調整
1回20~30分、週1~2回を目安
◎灸法
温灸・艾炷灸で腹部・背部の陽気を補う
特に冷えを伴う下痢型や腎虚型に効果的
手技・気の導引
4. 治療期間・効果判定
個人差があるが、慢性IBSの場合は週1~2回、3か月程度の継続施術で改善を確認することが多い。
主な効果:
腹部膨満感の減少
便通の安定(下痢・便秘の交互発作の軽減)
精神的緊張の緩和(肝気鬱結型)
5. 西洋医学との併用
東洋医学的施術は、症状の緩和・体質改善を主目的とする。
下痢型・便秘型などの薬物療法と併用することで、相互補完的な効果が期待できる。
心理的ストレスが関与するIBSでは、鍼灸+生活指導・呼吸法・食事指導が有効。
6. 文献・根拠例
R. Manheimer et al., “Acupuncture for Irritable Bowel Syndrome,” Cochrane Database Syst Rev, 2012.
Liang, F. et al., “Clinical observation of acupuncture in IBS treatment,” Journal of Traditional Chinese Medicine, 2017.
Zhu, J. et al., “Mechanism of acupuncture in gastrointestinal disorders,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2020.
7.橋本鍼灸院の鍼灸施術
橋本鍼灸院では、上記をベースに各人の体質をよく観察して、適切なツボを選択して、施術していきます。

西洋医学の過敏性腸症候群の解説
原因
明らかな原因はいまだ不明である。小腸や大腸からなる腸は食べ物を消化・吸収するだけではなく便として排出する機能も持っているが、この食べ物を排出する方向へ移動させるための腸の収縮運動はストレスなど不安な状態になると、運動が過剰になったりけいれん状態になったりして同時に痛みを感じやすい状態になる。過敏性腸症候群の患者は特に痛みを感じやすく、そのため腹痛になりやすいのが特徴だ。ストレスが原因で大腸の運動機能が障害される可能性や、刺激を腹痛として感じる脳の方が過敏になっている知覚過敏説などさまざまな原因が考えられているが、過敏性腸症候群になる原因はわかっていない。ただ、細菌やウイルスが原因となる腸炎にかかった場合、回復したあとに過敏性腸症候群になりやすいことがわかっている。
症状主な症状は腹痛や腹部の不快感、便秘や下痢などの便通異常で、ストレスによって悪化する場合が多い。便秘が続いたり、逆に下痢になりやすいなど患者によって症状がさまざまで、排便の回数と便の形状から「便秘型」「下痢型」「混合型」「分類不能型」に分けられる。型によって症状の出方も違い、例えば便秘型の患者の場合はストレスを感じると便秘が悪化するのに対して、下痢型の患者の場合は緊張してお腹を下す。対して混合型の患者は下痢や便秘を繰り返して、便の状態が変動する。過敏性腸症候群の患者は、そうでない人に比べて胃の痛みや胃もたれ、胸やけや胃食道逆流症を合併する人が多いと指摘されている。
治療
治療においては生活習慣の改善が重視される。暴飲暴食や深夜の食事、脂肪分の多い食事を避けて3食規則的な食事を心がける。また刺激物やアルコールも控え、できるだけストレスをためないようにしっかり睡眠を取って休養し、適度な運動や趣味などでリフレッシュすることも有効。必要に応じて、腸の運動を整える薬、ビフィズス菌や乳酸菌などの腸の運動を助ける薬や漢方などが処方される場合も。下痢型の患者には腸の運動を改善させる薬や下痢止めが、便秘型の場合には便を柔らかくする薬や補助的に下剤が用いられることもある。過敏性腸症候群の原因の1つとして食物アレルギーの可能性も挙げられており、抗アレルギー薬も選択肢の1つである。また心理的な不安が強い場合は抗うつ薬や抗不安薬が処方される場合もあり、患者に合わせて複数の薬を組み合わせた投薬治療が実施される。
予防/治療後の注意
過敏性腸症候群を予防できたという研究はないが、過敏性腸症候群になりやすい要因を避けるという対策は可能だ。要因の1つとして挙げられるストレスを減らす。また食事においても暴飲暴食は避けて、脂肪分や肉類が中心のメニューではなく野菜や乳酸菌を適度に摂取できるメニューを心がける。睡眠や休養をしっかり取るなど規則正しい生活習慣が予防につながる。またアルコールに頼らないリフレッシュ方法を見つけて実践するなど、日常的な取り組みが効果的だ。