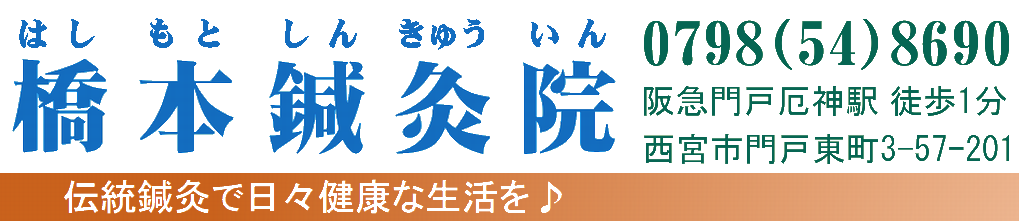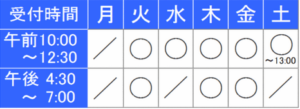起立性調節障害とは
起立性調節障害(きりつせいちょうせつしょうがい)(orthostatic dysregulation, OD)は、起立時の不調を中心とする症状群で、本邦では小児科でよく用いられる。原因は十分に明らかにされていないが、血管迷走神経失神/神経調節失神の1型と考えられている。起立試験を行い、循環器系を含めた症状再現を確認する。一般に良性であり、適切な治療や支援を行うことによって回復する。10歳から16歳に多く、日本の小学生の5%、日本小児心身医学会によると、“中学生の10人に1人”いるとされ、男女比は 1:1.5〜2 と報告されている。概日リズムが5時間程度うしろにズレていることが多く、『宵っ張りの朝寝坊』になりやすい。また、上気道のアレルギーを併発する割合が高いとする報告がある。【ウィキペディア引用】
🟢橋本鍼灸院では、東洋医学に基づいて、上実下虚(上半身が緊張して、下半身が弱っている状態)、ストレス、胃腸の弱り、などが原因と考えます。上実下虚は、手足の鍼でアンバランスを整えます。ストレスは、百会・後谿・太衝穴で対応します。胃腸の弱りは太白・脾兪で対応します。各人ごとに体質が少しづつ異なるので、症状・脈・舌などを参考にして、適切なツボを選択して、丁寧に対応していきます。このページの下に、詳しい東洋医学の考え方・施術方法を記載しています。
症例
🔵症例:中学生男子
中学校にはいってから、朝が起きれない、倦怠感、微熱が続き、次第に登校できなくなってくる。なかなか改善しないので、橋本鍼灸院に来院される。身体を調べると、体質的に過敏で、ストレスを受けやすいことと、上半身が緊張して下半身が弱っている状態でした。手と足に一番細い鍼でごく浅く鍼をして、緊張を取りながら下半身を補う施術を継続しました。徐々に原気になっていき、3か月ほどで徐々に登校できるようになってきました。後は無理をせずに本人のペースで生活することが大事ですので、焦らずに鍼施術を継続していくことが大事です。
🔵その他症例も色々あります。試験と塾の勉強でオーバーワークのために集中できなくて朝が起きれなくなった女子など。タイプとしては、体力があるが緊張しやすくて症状がでる人と、体力が低下して症状がでる人がいますので、体質の違いを見極めて施術していきます。
🟢起立性調節障害の鍼は、過敏な体質ですので、最も細い鍼を1mm以下で刺入しますので、まったく痛みなく施術をうけることができます。またそれでも鍼が怖いという学生や非常に過敏な体質の人には、打鍼で腹部のみの接触鍼で施術することもできます。
※記載の西宮・橋本鍼灸院の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。
東洋医学に基ずく鍼灸施術
1.東洋医学における病因・病機の考え方
起立性調整障害は、東洋医学的には以下のように捉えられます。
◎気虚(特に脾気虚・心気虚)
メカニズム~気が不足し、血行を推し進める力が弱いため、立ち上がり時に血が頭部に巡らずめまいが起こる。
症状~疲れやすい、食欲不振、顔色不良、朝起きられないなども一致。
◎気血両虚
メカニズム~成長期の過労・睡眠不足・偏食などで気と血がともに不足し、脳や心に栄養が届かない。
◎腎虚
メカニズム~腎は「先天の本」であり、自律神経・ホルモン系に関わる。成長期の発育不全や虚弱体質があると腎気不足で調整力が弱まる。
◎肝鬱・気滞
メカニズム~学校ストレスや精神緊張で「肝気」が滞り、自律神経失調が助長される。
2.治療方針
◎基本方針
「補気養血」「調和心腎」「疏肝解鬱」「安神」を中心とする。
気血のめぐりを整え、自律神経のバランスを回復させる。
◎治療原則
朝の起床困難 ➡ 脾胃を補い気を充実
めまい・立ちくらみ ➡ 気血を上に巡らせる
動悸・不安感 ➡ 心腎の調和・安神
頭痛や倦怠 ➡ 肝気の疏通
3.よく用いられる経穴
(1)補気養血
◎足三里(ST36):脾胃を補い全身の気血を充実。
◎気海(CV6):下丹田、元気を補う。
◎脾兪(BL20)、胃兪(BL21):脾胃を補強。
◎三陰交(SP6):血を養い、自律神経安定。
(2)心腎を調える
◎心兪(BL15)・腎兪(BL23):心腎相交を促す。
◎神門(HT7):安神作用。
(3)肝気の疏通
◎太衝(LR3):肝気の鬱滞を緩める。
◎膈兪(BL):胸中を開き、不安感・動悸に。
(4)頭部症状への配穴
◎百会(GV20):気を上に引き上げ、めまい改善。または安神作用で精神を安定させる。
4.施術方法
◎手技
基本は補法主体(軽い刺激・温かみのある補の鍼)。
虚証傾向が強いので、過剰な瀉法は避ける。
◎灸
太白・気海・関元などにお灸を加えて気を補う。
虚寒体質の場合は特に有効。
5.治療の流れ
◎初診時:脈・舌・腹診を行い「虚実・寒熱・気血水・五臓の虚実」を把握。
週2回を目安に継続して症状改善と共に間隔を空けていく。
◎自宅養生指導:規則正しい生活、朝日を浴びる、少量の運動、バランスの良い食事を推奨。
6.養生指導(鍼灸と並行して行う)
◎朝のリズム作り:朝日を浴びて自律神経のリセット。
◎睡眠:夜更かしを避ける。
◎食事:脾胃を補う「米・芋・豆類」を中心に。甘いもの・冷たいものを控える。
◎運動:軽い有酸素運動で気血循環を助ける。
◎心理ケア:ストレスを和らげる工夫。
まとめ
西宮の橋本鍼灸院では、起立性調整障害に対する東洋医学の鍼灸を 「虚を補い、気血を調え、肝腎を養い、心を安定させる」 ことを目標に行われます。
小児や思春期に多いことから、刺激はやさしく、養生と並行することでより効果が期待されます。