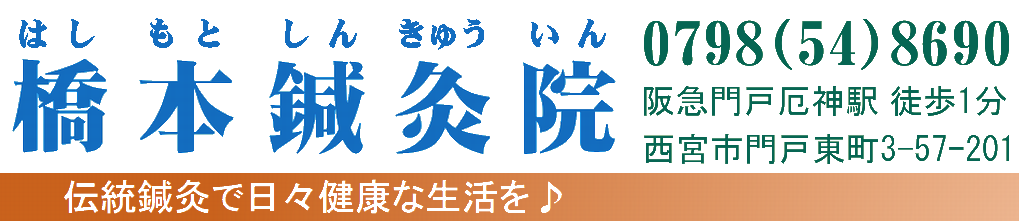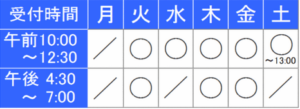症例
めまいは非常に多い症状です。特に女性によく見られます。鍼灸的な原因は、ストレス、身体の左右のバランスが乱れている、身体の水の巡りが悪い、身体の上下のバランスが乱れている、体力の低下などです。疲労、不眠、頭痛、耳鳴りなどを伴うこともよくあります。
原因を明らかにして、鍼灸の施術で上記のバランスの乱れを調えていきます。東洋医学に基づく鍼灸施術については、下に詳しく解説しています。
■良性発作性頭位めまい症:50代女性
7年前よりめまいが起こりやすい。3カ月前より起き上がる時や寝返りでつよい眩暈が起こるようになる。嘔気と頭痛もする。薬で症状が改善しないので来院されました。
身体をみると上半身が緊張していて、下半身が弱っている状態でした。頭と足に鍼をして上下のバランスをとるように10回ほど施術しました。
■めまい:40代女性
すこし歩くとふわふわとめまいがする。服薬にて改善せず、左右のバランスが悪いとみて、手足に一本づつ鍼をして左右のバランスをとると5回ほど施術をしました。このようなタイプのめまいは、ストレスが身体の筋緊張などの左右差をおこして発症することが多く、鍼でバランスをとっていきます。
■血圧上昇によるめまい:70代男性
用事で忙しくストレスがたまっていた、降圧剤でコントロールしているが血圧上昇と共に頭が流れるような眩暈が起こってくる。収縮期血圧は170程度で、背部に鍼をして身体の緊張をゆるめるようにする。3回ほどの施術で血圧は130代に戻り、眩暈もましになりました。以降、血圧が上がった時に鍼をして症状は落ち着いている。
■ストレスによるめまい:40代男性
仕事が忙しく寝不足だった。急に回転性のめまいが起こる。血圧は正常。脈は弦脈をうち力強いが下半身をしめす脈は弱い。上下のバランスが悪いと考え、手のツボと足のツボに3回ほど鍼をしました。
※記載の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。
めまいの東洋医学に基づく鍼灸施術
めまいの東洋医学に基づく鍼灸施術について、詳しくご説明します。
1. 東洋医学におけるめまいの捉え方
東洋医学では、めまいは単一の原因ではなく、身体全体のバランスの乱れから生じると考えます。特に、以下のような臓器や物質の機能低下や滞りがめまいの原因とされます。
◎気(き):生命エネルギー。不足すると、脳へのエネルギー供給が不安定になり、ふらつきやめまいが生じます。
◎血(けつ):血液。不足すると、頭部や内耳への栄養供給が不足し、めまいや耳鳴りを引き起こすことがあります。
◎水(すい):体内の水分。代謝が悪くなると、余分な水分が体内に停滞し、めまいや吐き気を引き起こします。特に、内耳の水分代謝の乱れは、メニエール病などのめまいの原因にもつながると考えられています。
◎肝(かん):自律神経や感情、血の貯蔵・巡りに関わる臓器。ストレスや過労で「肝」の機能が乱れると、気が上逆し、回転性のめまいを引き起こすことがあります。
◎腎(じん):水分代謝や生殖機能、耳や骨に関わる臓器。機能が低下すると、ふわふわとした浮遊感のあるめまいや、耳鳴り、難聴などを伴うことがあります。
これらの要素が複雑に絡み合い、めまいの症状として現れます。そのため、鍼灸施術では、症状を一時的に抑えるだけでなく、根本的な体質改善を目指します。
2. 鍼灸施術の目的
めまいに対する鍼灸施術の主な目的は、以下の通りです。
◎気・血・水の巡りの改善:経絡(気の通り道)の流れを整え、滞りを解消することで、脳や内耳への血流やエネルギー供給を促進します。
◎自律神経の調整:ストレスや睡眠不足で乱れた自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスを整え、心身をリラックスさせます。
◎筋肉の緊張緩和:首、肩、後頭部などの筋肉の過剰な緊張を和らげ、血行不良を改善します。
◎内臓機能の強化:「肝」や「腎」など、めまいに関連する内臓の機能を高め、根本的な原因にアプローチします。
3. 具体的な施術内容と使われるツボ
患者さんのめまいの種類(回転性、浮動性など)、付随する症状、体質などを詳しく診察し、適切なツボを選びます。
■ 局所のツボ(頭部や首周り)【橋本鍼灸院では、基本的に局所に鍼はしません。かえって気が上に昇ることが多いので、腹部・背部・下肢にツボを選択します。】
◎百会(ひゃくえ):頭のてっぺんにあるツボ。頭部全体の血流を促し、めまいや頭痛、不眠など多くの症状に効果があるとされます。
◎風池(ふうち):後頭部の髪の生え際、首の筋肉の外側にあるツボ。首や肩のこり、頭痛を伴うめまいに効果的です。
◎翳風(えいふう):耳たぶの後ろのくぼみにあるツボ。耳鳴りや難聴など、耳に関連するめまいに用いられます。
■ 全身のツボ(遠隔のツボ)
◎内関(ないかん):手首の内側、しわから指3本分下にあるツボ。めまいだけでなく、吐き気や乗り物酔いにも効果があるとされ、自律神経の調整にも役立ちます。
◎太衝(たいしょう):足の甲、親指と人差し指の骨の間にあるツボ。「肝」の経絡に属し、ストレスやイライラが原因のめまいに効果的です。
◎豊隆(ほうりゅう):すねの外側、膝と足首の中間にあるツボ。体内の余分な水分(痰濁)を取り除くのに用いられ、胃腸の不調を伴うめまいに有効です。
◎太渓(たいけい):内くるぶしの後ろ、アキレス腱との間にあるツボ。「腎」の機能を高め、フワフワしためまいに効果があるとされます。内くるぶしの下にある照海(しょうかい)穴もよく用います。
これらのツボに鍼を刺入したり、お灸を据えたりして、気の巡りを調整します。
4. 施術の流れ
1. 問診と診断:めまいの発症時期、頻度、症状の質(回転性か、浮動性か)、随伴症状(吐き気、耳鳴り、頭痛、肩こりなど)、生活習慣、ストレスの有無などを詳しく聞き取ります。
2. 東洋医学的な診断:脈診、舌診などを行い、患者さんの体質や根本的な原因を把握します。
3. 施術:問診と診断に基づいて、症状や体質に合わせたツボに鍼や灸を施します。
4. セルフケア指導:めまいを起こしにくい身体にするための、自宅でのツボ押しや生活習慣のアドバイスを行います。
5. 注意点
◎ めまいは、脳梗塞や脳出血などの重篤な疾患が原因で起こることもあります。まずは医療機関を受診し、命に関わるような病気ではないことを確認することが最も重要です。
◎ 鍼灸治療は、慢性的なめまいや、病院で「原因不明」と診断されためまいに対して、特に有効なアプローチとなり得ます。
◎ 症状の改善には個人差があり、継続的な治療が必要となる場合が多いです。施術の頻度や期間については、初診時にご相談いたします。
◎ 西宮の橋本鍼灸院では、各人の状態をよく観察して、適切なツボを厳選して施術していきます。