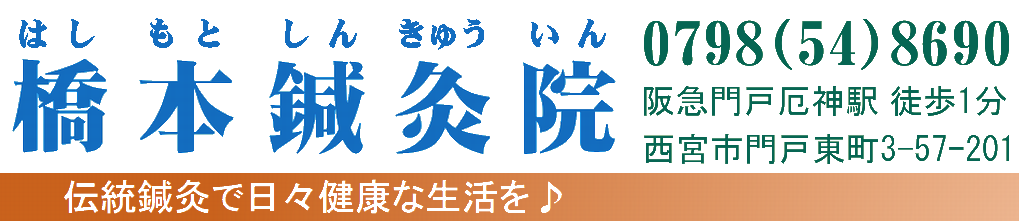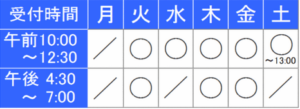症例
■喘息:70代男性
30年以上前から喘息を患い、長年ステロイド吸入をしている。今年になって夜中に痰が多量に溜まり咳が出て、目が覚めなかなか切れなくて眠れない。
身体をみると、脈は大きくつよく打ち、舌の苔が厚くなっていて舌の色は赤く、身体に湿が溜まり気管支の炎症もつよい状態でした。また夜に身体が熱くなり手足が火照ることと脈の状態から漢方でいう腎虚がありました。
手の肺の炎症をとるツボと、足の腎虚を治すツボを用いて、週2回10回ほど鍼を行いました。その後症状の再発予防で週に1回来院されています。
■小児喘息:小学低学年の女子小さい頃より風邪をひくと気管支炎になっていた。半年前に風邪をひいてから咳が止まらず喘息といわれる。入院してステロイド療法を行う。一旦よくなったが2か月後に喘息発作で1週間入院する。現在もタルミコート、メプチンを使用しているが咳が続いている。腹部に喘息特有の反応が出ていたので、腹部への打鍼(刺入せずに緊張したところを刺激する鍼)を行う。20回ほど施術を継続されました。
■小児喘息:6歳男児 生活環境の変化に伴い、4歳ごろから喘息を発症。吸入を毎日していた。寝つきが悪い、疲れやすいなどを主訴に鍼灸を始めた。週に1・2回の施術を継続しました。喘息は吸入をしないと発作が出ていたが、鍼をはじめてから吸入しなくても発作が徐々に出なくなり、喘息が悪化する秋になっても発作がでなくなる。喘息を意識して施術をしていませんが、鍼施術によりアレルギー体質(この子供さんの場合は、鍼灸では上実下虚の体質だった)がよくなり発作が起こらなくなったものと考えています。
■ストレスからの咳症状:小学校5年生男児半年前より咳症状が毎日継続する。学校に行っている間が特にひどい。呼吸器科で喘息の疑いがあるのでステロイド吸入を進められたので、来院。脈が滑弦で堅い。舌は赤く緊張をしめす紅点が多い。腹部も上部を中心に緊張している。過緊張から気管支が過敏になっているものとして、腹部に打鍼(刺入せずに緊張したところを刺激する鍼)をする。20回ほど施術を継続しました。
■東洋医学による鍼灸施術
東洋医学における喘息治療は、単に症状を抑えるだけでなく、根本的な体質改善を目指すものです。鍼灸治療では、西洋医学とは異なる独自の視点から、身体のバランスを整えることで喘息の発作を予防し、症状を緩和します。
■ 東洋医学から見た喘息
東洋医学では、喘息は単なる呼吸器系の問題とは捉えられません。体内の「気・血・水」のバランスが崩れた結果、「肺」「脾」「腎」といった臓腑の機能が低下し、痰が生成されたり、気の流れが滞ったりすることで発症すると考えられています。
◎ 肺: 呼吸をつかさどる最も重要な臓腑。肺の機能が弱ると、外邪(風邪や冷えなど)が侵入しやすくなり、咳や呼吸困難を引き起こします。
◎ 脾: 飲食物からエネルギー(気)や水分を生成し、運搬する働きがあります。脾の機能が低下すると、余分な水分が体内に停滞し、それが痰となって肺に溜まりやすくなります。
◎ 腎: 体内の水分代謝や、呼吸の「納気」(気を深く吸い込む力)を司ります。腎の機能が衰えると、呼吸が浅くなり、特に発作時に息を吸い込む力が弱まります。
これらの臓腑の弱りや、冷え、湿気、ストレスなどの影響で、体質がいくつかのタイプに分類されます。
■ 鍼灸施術の基本原則
鍼灸治療では、患者さんの個別の体質や病態を詳細に診断し、そのタイプに応じて施術を行います。一般的な治療の原則は以下の通りです。
1. 肺気を整える: 肺の機能を高めるツボ(経穴)に鍼やお灸を施し、呼吸を楽にします。これにより、咳や息苦しさの緩和が期待できます。
2. 脾の働きを助ける: 脾の機能を回復させるツボを刺激することで、痰の生成を抑え、体内の余分な水分を排出しやすくします。
3. 腎を補う: 腎の働きを強化し、呼吸を深く、安定させることを目指します。特に慢性的な喘息や高齢者の喘息に有効です。
4. 気の流れをスムーズにする: ストレスや感情の変動が原因で発症する喘息には、自律神経を整え、全身の気の巡りを良くするツボを使用します。
■橋本鍼灸院で使用される代表的なツボ
橋本鍼灸院では、上記の原則に基づき、特定のツボをよく使用します。
◎ 心兪(しんゆ): 背部第五胸椎横にあるツボ。咳や呼吸困難の緩和に即効性があると言われています。
◎ 尺沢(しゃくたく): 肘の内側にあるツボ。肺の熱を取り、咳や痰を鎮める効果が期待できます。
◎ 列缺(れっけつ): 手首上の親指側にあるツボ。肺の機能を高め、慢性的な咳を改善、咳や痰を鎮める効果があります。
◎ 豊隆(ほうりゅう): 下腿の外側にあるツボ。痰の排出を促し、身体の湿気を取るのに効果的です。
◎ 腎兪(じんゆ): 腰部にあるツボ。腎の機能を補い、呼吸を安定させるために使用されます。
これらのツボに鍼を刺したり、お灸で温めたりすることで、臓腑のバランスを調整し、体質を根本から改善していきます。
■ 鍼灸治療の進め方
治療は、発作時と寛解期(症状が落ち着いている時期)でアプローチが異なります。
◎ 発作時: 症状を緩和するために、即効性のあるツボに鍼を打ち、呼吸を楽にすることを最優先します。
◎ 寛解期: 次の発作を予防するために、体質改善を目的とした施術を行います。定期的に通院し、身体のバランスを整えることが重要です。
鍼灸治療は、西洋医学の治療と併用することも可能です。薬物療法に頼りたくない方や、体質そのものを改善したいと考えている方にとって、有効な選択肢の一つとなります。ただし、治療を受ける際には、必ず専門の知識と経験を持った鍼灸師に相談することが大切です。
※記載の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。