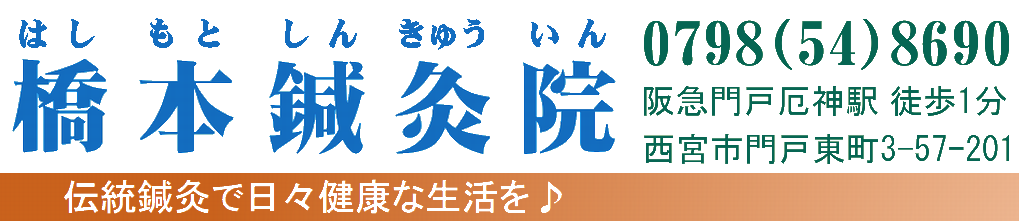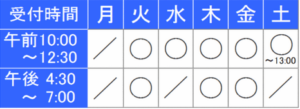橋本鍼灸院の東洋医学に基づく鍼灸施術
🟢東洋医学では、蕁麻疹は身体が熱に傾いて起こると考えます。熱に傾く原因は、ストレス、ニンニク・油濃いものなどの過食、暑がりな体質などがあります。舌は正常より赤くなり乾燥気味で、皮膚の温度は平均より高くなっています。鍼で身体の熱を冷ます施術とストレスを軽減する施術をしながら、食事内容を改善していくことで対応します。詳しい東洋医学の鍼灸施術は、下の方に記載しています。
症例
■ストレスからの蕁麻疹:30代男性。半年前より上肢・腹部・背部・大腿内側が急に痒くなり赤疹がでるようになる。仕事で緊張した後に急激に痛みを伴い症状が出現。抗ヒスタミン剤を服用するが全く改善しない。緊張した後や気温上昇や午前中に症状がでやすい。食事が油濃いもの、香辛料が多い。その他首の凝り・喉のつまりがある。舌暗紅瘀斑、脈滑実、右肝相火緊張。仕事のストレスによる肝鬱火化を主として陽熱の飲食も関係する心肝火旺証とする。背部に一本、鍼をする。8回ほどで症状は落ち着きました。
■皮膚アレルギー:8ヶ月男児 乳児性湿疹から皮膚の食物アレルギーを発症。ステロイドを繰り返し使用するが次第に強いものになり効果もなくなってくる。身体をみると足や背部のツボの反応から胃腸の働きが弱っているために治りにくいと考えた。てい鍼という刺さない金属の棒で炎症をとり、胃腸の弱りを調整した。週に2回継続して鍼をすることで20回程で終了としました。
■蕁麻疹:小学生女子
以前よりぶどう・キウイで口が痒くなるアレルギーがあった。今回、スモークサーモン・サケフレークを食べてから口が痒くなり次いで背部全体、上肢が赤く腫れてつよい痒みがでてくる。
8カ月間抗ヒスタミン剤、レスタミンコーチゾン軟膏などを使用するが一進一退でよくならない為、来院される。
身体の状態をみると、舌は通常より赤く苔がすこし厚く、脈はつよくて早く、口渇して冷飲するので身体が炎症傾向であり、鍼灸での脾胃湿熱証とする。
小児鍼では十分に炎症がとれないので、細い鍼を背部の脾胃の炎症をとるツボに1本する。
来院ごとに痒み・炎症はましになってきたが、取れきれない為、足の炎症をとるツボを加えて施術する。
遠方の為、週に1回の鍼を継続し、10回ほどで症状が落ち着きました。
■蕁麻疹:20代女性
中学生の頃より度々蕁麻疹がでている。2カ月前より大腿内側に発赤・痒みがでていた。数日前から大腿、腰部、胸部、首周りにつよい痒みと湿疹がでてくる。抗ヒスタミン剤で少し軽快したがそれから改善しないので来院される。
身体の状態をみると鍼灸の見立てでストレスに加え胃腸に熱があるためにハウスダストなどのアレルゲンに反応して発症したものとしました。
身体の緊張と胃腸の熱を同時にとる背部のツボに鍼をして、7回ほどで施術をしました。
※記載の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。
蕁麻疹の東洋医学に基づく鍼灸施術
蕁麻疹に対する 東洋医学に基づく鍼灸施術 について、弁証論治の観点から詳しく整理してご説明します。
1. 東洋医学における蕁麻疹の理解
蕁麻疹は、皮膚に一過性の膨疹(赤み・かゆみ・腫れ)が現れ、数時間で消退し、再発を繰り返す病態です。
東洋医学では以下の要因が重視されます。
🔴風邪(ふうじゃ):皮膚表面を巡る「衛気」の防御機能が弱ると、風邪が侵入し皮膚にかゆみや発疹を生じる。
🟢湿邪・湿熱:飲食の不摂生や脾胃の機能低下により湿が生じ、皮膚に熱を帯びて発疹が出やすくなる。
🔵気血の不和:血虚や瘀血があると皮膚の栄養不足や巡りの停滞で慢性化。
🔴ストレス・肝鬱化火:情志(ストレス)の停滞により肝気が鬱し、熱を帯び皮膚に影響する。
2. 弁証タイプと施術方針
① 風寒型(急性・寒冷で悪化)
◎特徴:寒冷刺激で悪化、白っぽい膨疹、温めると軽快
◎施術方針:表を温めて風寒を散らす
◎主な経穴
風門(膀胱経)
大椎(督脈)
合谷(大腸経)
② 風熱型(急性・熱感、赤みが強い)
◎特徴:鮮紅色の膨疹、熱感、かゆみが強い、発熱を伴うことも
◎施術方針:清熱解表、風邪を散らす
◎主な経穴
曲池(大腸経)
合谷(大腸経)
大椎(督脈)
血海(脾経)
三陰交(脾・肝・腎の交会穴)
③ 湿熱型(慢性化しやすい・飲食や胃腸由来)
◎特徴:かゆみが強く、食事(アルコール・油物・甘味)で悪化、舌苔が黄膩
◎施術方針:健脾利湿・清熱解毒
◎主な経穴
公孫(脾経)
天枢(大腸経)
陰陵泉(脾経)
上廉(胃経)
血海(脾経)
④ 気血両虚・血虚風燥型(慢性・再発性)
◎特徴:繰り返し出る、夜間に悪化、乾燥肌、不眠や疲労を伴う
◎施術方針:補気養血、滋陰潤燥、風を止める
◎主な経穴
気海(任脈)
脾兪(膀胱経)
腎兪(膀胱経)
三陰交(脾・肝・腎)
照海(腎経)
3. 補助療法
◎灸療法:寒冷誘発型には温灸(足三里・中脘・脾兪など)
◎生活養生:
冷え・ストレス・睡眠不足を避ける
食事で甘味・脂っこい物・アルコールを減らす
生野菜をよく食べて身体の熱をさます。特にキャベツは性質が平性なので、身体を冷やさずに内熱をとります。
冷たい飲食や刺激物も控える
4. 臨床上の工夫
◎急性期は「邪気を去る」ことを重視し、表の風熱・風寒を取る。
◎慢性・再発例は「本治(体質改善)」が中心で、脾胃・肝腎を補う。
◎「皮膚は肺と関係が深い」とされ、肺経の経穴(列缺・孔最など)を用いる場合もある。
5.まとめ
👉 まとめると、蕁麻疹に対する東洋医学の鍼灸は
◎急性 → 風寒・風熱を散らす
◎慢性 → 脾胃を健やかにし、気血を調える
という二本柱で施術を進めます。