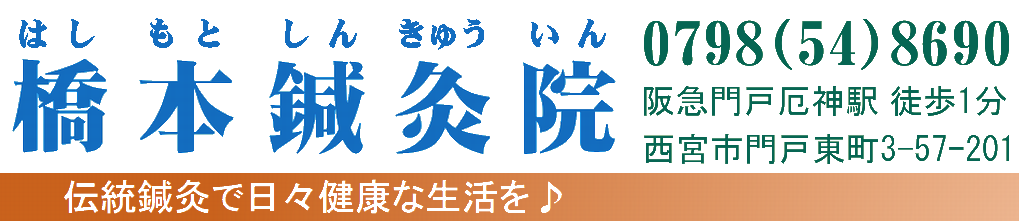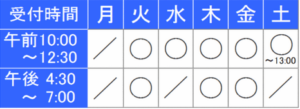症例
30代男性。10年程前より、潰瘍性大腸炎で西洋医学の治療を受けているが、ステロイドの量が増えて、鍼治療を併用してほしいと来院される。下血と腹痛が継続している。身体を調べると、背部・腰部の緊張がとてもつよく、同時に胃腸の働きが弱っていた。鍼灸では、「肝」が亢進して、「脾胃」が弱っていると考えて、背部と足の太白穴に鍼をしました。10回ほどで下血は止まり、腹痛もその後消失しました。週に一度根気よく施術して、その後ステロイドも休止することができました。
🟢多くの場合、潰瘍性大腸炎は上記の方のように、ストレスで身体がつよく緊張していて、同時に胃腸の働きが弱っていることで発症しています。身体の緊張をとると同時に胃腸の働きを改善することで徐々に体質改善されて軽快していくことが多いですね。
※記載の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。
東洋医学(TCM/中医)に基づく潰瘍性大腸炎(UC)の鍼灸施術
橋本鍼灸院では、以下の研究機関で行われている一般的な施術内容を参考に、施術しています。
多くは、肝鬱気滞と大腸湿熱と大腸機能の低下による症状がみられますので、各人の症状にあわせて最適なツボを厳選して施術します。
■東洋医学(TCM)での病態観 — 弁証(診断の枠組み)
TCMは症状を“証”に分類し、証に応じて治則(治療方針)と処方(穴位・方法)を決めます。UCで報告される主な証と代表的所見は以下です(臨床では混在することが多い)。
◎大腸湿熱【大腸の炎症】
便に粘血・頻回の下痢、腹痛、発熱感、口苦、舌苔黄膩。
治則:清熱利湿、瀉火解毒。
◎脾虚失運【大腸機能の低下】
下痢が慢性化、疲労倦怠、食欲不振、顔色萎黄、舌淡白。
治則:健脾益気、固腸止瀉。
◎肝気鬱結化火【ストレスから炎症が悪化】
腹部痙攣性痛、情緒ストレス先行、便に血、口渇、胸脇苦満。
治則:疏肝理気、清肝火、止血。
◎陽虚寒湿/腎陽虚(重症や冷えを主体とするもの)
下痢に冷感、四肢冷え、舌胖大、脈沈微。
治則:温腎散寒、補陽固表。
【多くは上記の最初の3つの状態が同時にみられます】
■ 鍼灸の治療原則
◎清熱利湿・解毒止血:粘血下痢・鮮血が目立つとき。
◎健脾益気・固腸止瀉:慢性活動期を過ぎて体力低下し下痢が主体のとき。
◎疏肝理気・調和肝脾:ストレス関連の悪化を伴うとき。
◎温陽散寒:冷えや陽虚が強い場合。
上の治則に対応して穴位や手技(補法・瀉法、灸法の温熱など)を組み合わせます。
■ 臨床でよく使う穴位(具体的処方)
基本の経穴(中国で一般的によく用いられているもの)
天枢(ST25)… 大腸の募穴。腹痛・下痢、血便に中心的に使用。
足三里(ST36)… 補気健脾、免疫・消化機能の改善を狙う。多くの研究で主要使用点。
上巨虚/下巨虚(ST37/ST39)… 大腸の下合穴。下痢・大腸症状に。
中脘(CV12)、関元(CV4)… 胃腸の中枢調節や補気作用。
大腸兪(BL25)、脾兪(BL20)… 背部の兪穴で腸の機能を支持。
合谷(LI4)・太衝(LR3)… 疏肝理気・止痛に併用。
三陰交(SP6)… 瀉下・停水・全身調整に有用。
【橋本鍼灸院では、長年の臨床経験に基づき、多くは百会、後溪、公孫、膈兪、至陽などから選択して施術します。上記のツボとほぼ同じ働きがあります。】
■ 手技・施術方法
(A)鍼法~省略
(B)灸法【橋本鍼灸院では、ほとんど用いません】
隔物灸(薬物隔物灸/薬餅灸):腹部(天枢や中脘)に薬草や生姜を介して温熱刺激を行い、健脾温陽・止瀉効果をねらう。臨床報告が多い。
直接灸/間接灸:寒象や陽虚が強い場合に使用。
(C)頻度・コース(臨床研究例)
急性活動期:週2–3回、6〜8週を一コースとする報告が多い。
慢性/維持期:週1回〜隔週、数か月にわたる維持療法や埋線での長期管理も報告あり。
複数のRCT/メタ解析は、6週間以上の継続治療で効果が顕著になることを示唆しています。
【症状が落ち着くまでは週に2~3回を継続されるのがいいです。服薬の上、症状が消失してきたら、医師の指示に従い減薬していきます。】
■ 生物学的メカニズム(研究で示されていること)
最近の基礎・トランスレーショナル研究は、鍼灸が以下を介してUCに作用すると示唆しています:
◎腸管バリア修復、上皮細胞機能改善。
◎炎症性サイトカイン(IL-6, TNF-α など)の低下・免疫細胞(マクロファージ極性)調節。
◎自律神経(副交感/迷走神経)を介した腸炎抑制(電気鍼で副交感系活性化の報告)。
ただし、これらは多くが動物実験や小規模ヒト研究であり、臨床的因果関係を完全に立証する段階には至っていません。
■ 実際の臨床での使い方(安全性・他治療との併用)
◎他の薬物療法(5-ASA、ステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤)とは原則併用可能。ただし増悪時はまず西洋医学的評価(内科的検査・コロノスコピー等)を優先し、重症例では単独で鍼灸に頼らない。鍼灸は補助療法・症状緩和・QOL向上の位置づけが現実的。
◎副作用・禁忌:出血傾向(抗凝固薬内服)、重度の免疫抑制、皮膚感染部位、妊娠初期などは注意。灸はやけどリスクがあり熱感に敏感な患者は慎重に。
■ 臨床で期待される効果と現実的なメッセージ
◎臨床試験は症状の軽減・再燃抑制・炎症マーカー低下などを示すが、効果の大きさや持続性は個別差がある。
◎鍼灸を選ぶなら:施術経験のある鍼灸師が望ましい。重症化や発熱、頻回の血便がある場合はまず消化器専門医を受診すること。
以下は本回答で根拠として参照した、主要な査読論文・総説・ガイドラインです。まずはこれらを参照すると臨床・研究の理解が深まります。
Wang et al., 2020. Acupuncture for ulcerative colitis: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. BMC Complementary Medicine and Therapies.(系統的レビュー).
Zhao et al., 2021–2024. 各種レビュー:鍼灸・灸法が腸粘膜修復、免疫調整に与えるメカニズムを解説した総説群(Frontiers, Pharmacol. / Heliyon 等)。
Hao J. et al., 2023. Electroacupuncture for ulcerative colitis patients: A meta-analysis and acupoints selection study.(EAのメタ解析と経穴解析).
Scoping reviews / clinical reviews: Review of Clinical Studies of the Treatment of Ulcerative Colitis by Acupuncture and Moxibustion(2016)など、臨床研究の総覧。
国際/中国のTCMガイドライン・総説:TCMをUCに応用する国際臨床実践ガイドラインや中国の診療ガイドライン(近年版)。
(上の項目のリンクはこのチャットの出典番号と対応します。特に臨床効果の総括は1・3・4の系統的レビューに基づきます。)
■最後に
鍼灸は補助療法として有用性の根拠が増えており、特に腹痛・下痢のコントロールやQOL改善の目的で検討に値します。だが「標準治療の代替」とするにはまだ十分な高品質エビデンスが不足しています。
実施する場合は消化器内科医と連携、基礎検査で重症化リスク評価(出血・発熱・貧血・電解質異常など)を行ってください。