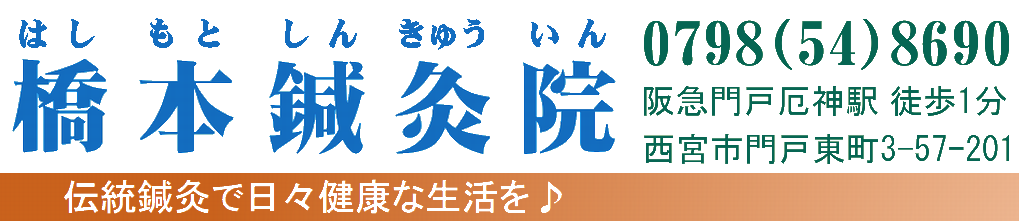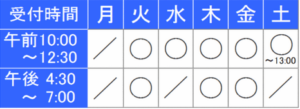症例
■倦怠感・微熱・五月病
30代女性。ゴールデンウイーク後からつよい倦怠感、微熱、頭痛などが続く、血液検査は正常だった。症状が取れないところに風邪を引いて熱はないが咽痛がつよく、咳、頭痛・腰痛もでてきたので、8月に来院される。
身体の状態をみると、脈が浮いているが細くて弦脈であり、自汗していました。背部は全体に緊張しているが特に右の膈兪あたりの緊張が強い。
脈が浮いているので太陽病(鍼灸での感染症の証名)であるが、同時に弦脈を呈しているので、太陽少陽の合病として申脈・後谿に鍼をしました。施術後、脈は緩み浮いた脈は中位にもどり、倦怠感と頭痛・腰痛が少しましになったという。以降週に1・2回鍼をして、風邪は2回でよくなり、従来からあった倦怠感も徐々に落ち着きました。これはストレスによって症状があるところに風邪をひいて更に悪化した症例です。その後も肩こり・腰痛がでてきたら来院して体調を調えるようにされています。
■急に起こる首・肩の痛みと気分の落ち込み
50代女性。半年前より、肩こり・首の痛みがつよくなってきる。同時に顎関節症もおこり電気施術によりこれは軽快する。次に自律神経の調整をするマッサージをしてもらい継続した肩こりはましになるが、2日に1回の頻度で急に首・肩の痛みを出てきて同時に気分の落ち込みの症状が出てくるようになり、来院される。
身体を調べると、年齢に伴う下半身の弱りが根本原因であり、鍼灸でいう腎虚として鍼を足にしました。その後、健康維持のために時々鍼を継続して来院されています。
■めまい、胃の圧迫感、手足の冷え、下肢のだるさ、その他諸症状:20代女性就職して以来、上記の症状がでてきて、毎日がつらい。舌、脈、腹部、背部の経穴の状態やその他所見から、体力は充実しているが、身体の上が緊張し、左右の経穴のバランスが非常に悪い為に発症していると考え、手に鍼をする。10回ほど施術をしました。ただし仕事で無理をするとすこし症状が出てくるので、週に1回鍼を継続しました。
■慢性に継続する嘔気:10代女性 1年前より食後、歯磨きでも嘔気が起こるようになる。身体をみるとストレスもあるが、胃腸の弱りがあるので、足の消化機能をつよくするツボに鍼をする。10回ほど施術を行いました。
※記載の西宮・橋本鍼灸院の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。
自律神経失調症の範囲に含まれることが多い症候・疾患
※自律神経失調症 = 器質的疾患が見つからないのに自律神経のバランスの乱れで不調が出る状態の事で、以下の症候も自律神経失調症に含まれることがあります。
◎起立性調節障害(OD)
◎不整脈様症状(検査では異常が見つからない場合)【継続した鍼施術で対応します】
◎過敏性腸症候群(IBS)
◎機能性ディスペプシア(胃の不快感・胃もたれ)【五蔵の肝と胃のツボで対応します】
◎メニエール病やメニエール類似症状【めまいの鍼施術で対応します】
◎心因性めまい
◎神経性頻尿【腰部や足の鍼灸で対応します】
◎月経不順・更年期障害(自律神経・ホルモンの乱れが関連)
◎慢性疲労症候群・すぐ疲れる
◎不眠症(特に自律神経の過緊張による)
◎頭痛(緊張型頭痛・片頭痛の一部)
◎気象病~天候によって頭痛・めまい・倦怠感・浮腫が生じる【それぞれの症状に応じて対応します】
自律神経失調症とは(ウィキペディア)
西洋医学的に評価が定まっていませんので、わかりやすく説明しているウィキペディアを引用します。
■症状
めまい、冷や汗が出る、体の一部が震える、緊張するようなところではないのに動悸が起こる、血圧が激しく上下する、急に立ち上がるときに立ち眩みが起こる、朝起きられない、耳鳴りがする、吐き気、胃もたれ、頭痛、微熱、過呼吸、倦怠感、不眠症、生理不順、味覚障害といった身体症状から、人間不信、情緒不安定、不安感やイライラ、被害妄想、鬱状態など精神的な症状が現れることも多い。
自律神経失調症には様々な症状があり、病態は人それぞれの為、判断しにくい。どの症状がどれだけ強いのか弱いのかは患者それぞれである。患者によっては、その他の症状はあまり強く現れないにもかかわらず、ある特定の症状のみが強く表れる場合もあり、症状はきわめて多岐に亘る。■定義など
この病気は1961年ごろに東邦大学の阿部達夫が定義したものであるが、現在も独立した病気として認めていない医師も多い。疾患名ではなく「神経症やうつ病に付随する各種症状を総称したもの」というのが一般的な国際的理解である。
この病気は実際にはうつ病、パニック障害、過敏性腸症候群、頚性神経筋症候群や身体表現性障害などが原疾患として認められる場合が多く、原疾患が特定できない場合でもストレスが要因になっている可能性が高いため、適応障害とされることもある。■原因
薬物やアルコールの過剰摂取、著しい精神的ショックを起因とするもの、また女性では更年期が原因のホルモンバランスの乱れ等が挙げられるが、遺伝的に自律神経の調整機能が乱れている患者も存在するため一概に言う事は出来ない。しかし、少なくとも患者の半数は日常生活上のストレスがあると言われている。自律神経の中枢は脳の視床下部というところにあり、この場所は情緒、不安や怒り等の中枢とされる辺縁系と相互連絡していることから、こころの問題も関わってくる。
【ウィキペディアから引用】
東洋医学で考える自律神経失調症
■体質と自律神経失調症
東洋医学では同じ症状であっても、体質の違いを重要視します。
例えば、倦怠感でも体力のある人とない人では施術が異なります。体力のある人はストレスを緩めるような鍼をします。体力のない人は緊張を緩める施術はかえって症状が悪化するので、補法といって穏やかな刺激で胃腸の働きをつよくする鍼をします。
以上のように体力の有無、上実下虚の有無などを考えて施術しますが、タイプを以下のように分類します。
①肝鬱タイプ ~体力があるがストレスがつよい
②肝鬱脾虚タイプ ~体力は中程度で胃腸の働きが弱っている
③腎虚(上実下虚)タイプ ~足腰が弱ったりホルモンバランスが崩れているタイプ
④脾虚タイプ ~血圧が低く、胃腸が弱くて体力がないタイプ
自律神経失調症は、東洋医学では「気(き)」の巡りの乱れや、「臓腑(ぞうふ)」の機能不全が主な原因と考えられています。西洋医学では、自律神経のバランスが崩れることで様々な身体的・精神的な症状が現れるとされますが、東洋医学ではその根本的な原因を個人の体質や生活習慣から見つけ出し、全体的な調和を取り戻すことを目指します。
■東洋医学における自律神経失調症の考え方
東洋医学では、自律神経失調症は主に以下の臓腑の不調と関連づけられます。
* 肝(かん): ストレスや感情のコントロールを司る臓腑です。肝の機能が滞ると、「気滞(きたい)」と呼ばれる気の巡りが悪くなり、イライラ、怒りっぽい、胸や喉の詰まり感、不眠などの症状が現れます。
* 心(しん): 精神活動や血液循環を司る臓腑です。心の機能が弱まると、動悸、不安感、精神的な不安定、不眠などの症状が出やすくなります。
* 脾(ひ): 消化吸収をつかさどる臓腑です。脾の働きが低下すると、「気虚(ききょ)」と呼ばれるエネルギー不足の状態になり、倦怠感、食欲不振、消化不良などの症状につながります。
* 腎(じん): 生命エネルギーを貯蔵し、体の根本的な力を司る臓腑です。腎の機能が低下すると、体の水分バランスやホルモンバランスが乱れ、のぼせ、ほてり、めまいなどの症状が現れることがあります。
これらの臓腑のバランスが乱れることで、交感神経と副交感神経のバランスも崩れ、様々な不調が引き起こされると考えます。
■鍼灸施術の目的とアプローチ
鍼灸施術は、これらの乱れたバランスを調整し、身体の自己治癒力を高めることを目的とします。
* 「気」の巡りの改善: 鍼や灸を用いて、滞った「気」の流れをスムーズにします。特に、ストレスで気の巡りが悪くなっている「気滞」のタイプには、このアプローチが重要になります。
* 内臓機能の調整: 自律神経失調症に関連する肝、心、脾、腎などの臓腑の働きを整えるツボを刺激します。これにより、身体の内部からバランスを回復させます。
* 心身のリラックス効果: 鍼やお灸による穏やかな刺激は、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。これにより、不眠や精神的な緊張を和らげます。
* 血行促進: 鍼灸による刺激は、血行を促進し、冷えや手足のしびれなどの身体的症状を改善します。
■西宮・橋本鍼灸院で施術に使われる代表的なツボ
自律神経失調症の施術でよく用いられるツボには、以下のようなものがあります。
* 百会(ひゃくえ): 頭のてっぺんにあるツボで、全身の気の流れを整え、精神的な疲労や不眠に効果があります。
* 神門(しんもん): 手首の小指側にあるツボで、心を穏やかにし、不眠やイライラを和らげます。
* 太衝(たいしょう): 足の甲にあるツボで、肝の気の滞りを解消し、ストレス性の症状やイライラを鎮めます。
* 太渓(たいけい): 足首の内側にあるツボで、のぼせ、肩こり、動悸や腰痛に効果があります。
* 太白(たいはく): 足の親指の内側にあるツボで、胃腸の働きを整え、全身のエネルギーを補います。
これらのツボを、患者さん一人ひとりの症状や体質に合わせて組み合わせ、全身のバランスを調整する施術を行います。また、背中にある脊柱の両脇のツボ(心兪、肝兪、脾兪など)も、自律神経に直接的に働きかけるため、よく用いられます。
■施術の注意点
鍼灸施術は、自律神経失調症の根本的な体質改善を目指すため、即効性よりも継続的な施術が重要になります。また、鍼灸施術だけでなく、規則正しい生活習慣、適度な運動、ストレス管理などを併用することで、より高い効果が期待できます。橋本鍼灸院では、各人の体質を調べて最適なツボを厳選して施術します。